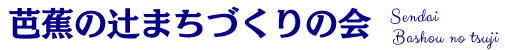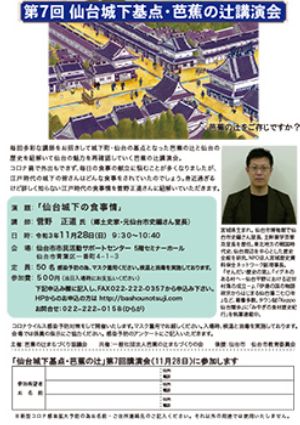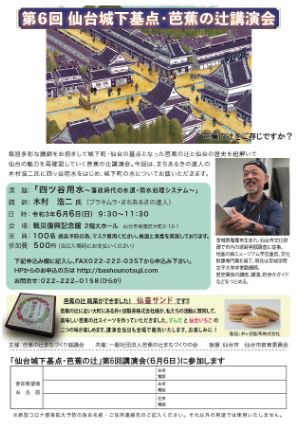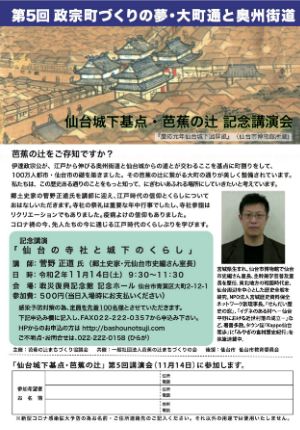これまで開催した講演会
まちを知れば、もっとまちが面白くなる。芭蕉の辻が仙台の城下町の基点ならば、そこからまちを知って行きましょう。芭蕉の辻まちづくりの会では、その道の達人に楽しくまちの歴史を学んでいきます。

第12回講演会「芭蕉ノ辻図二題」
」
12回目の講演会!
郷土の歴史を知ろうとはじまった芭蕉の辻講演会も回を重ね、12回目を迎えました。毎回楽しみにして足を運んでいただいた皆さんのおかげです。ありがとうございます。
仙台の城下町づくりの基点であった芭蕉の辻。辻の四隅に櫓のような二階建ての立派な建物があり、この辻の大きな特徴になっていました。その建築も維持管理の援助も藩がしていたようです。それはなぜか?異なる時期に描かれた二つの絵図を手掛かりに、まちあるきの達人・木村浩二氏がこの建物の目的や意味を解き明かします。

講師:木村浩二 氏
日時:令和6年9月15日(日)
10:00~11:30
会場:せんだいメディアテーク 7階スタジオシアター





第4回講演会「四ッ谷用水」
-江戸時代のインフラ整備と雨水処理システム-
仙台の城下町のインフラ水の確保について四ッ谷用水のお話をしていただく予定でした。
新型コロナウイルス感染拡大時期のため、泣く泣く中止いたしました。
これも時代を表す歴史なので、次回を4回目講演会とせず、私たちは第4回は中止として、会の歴史に残すことにしました。
 講師:木村浩二氏
講師:木村浩二氏
日時:令和2年4月11日(土)
9:30~11:30
会場:戦災復興記念館 記念ホール


第2回講演会「古地図の愉しみ 〜城下町仙台最後の姿~」
写真の無い時代の地図は、歴史を後世に伝える歴史を映し出す写真のようです。今ならパソコンですごく小さな文字も書き込むことが可能ですが、かなり大きな地図をつくり上げて筆で丁寧に書き上げる。先人のご苦労を感じつつ、そこに秘められた歴史のコンセキを紐解かれていきました。仙台の現在の街並みが伊達政宗が見ていた町割の上に乗って作られていることを感じる講演でした。
 講師:木村浩二氏
講師:木村浩二氏
日時:令和元年7月15日(月祝)
10:00~12:00
会場:戦災復興記念館 記念ホール